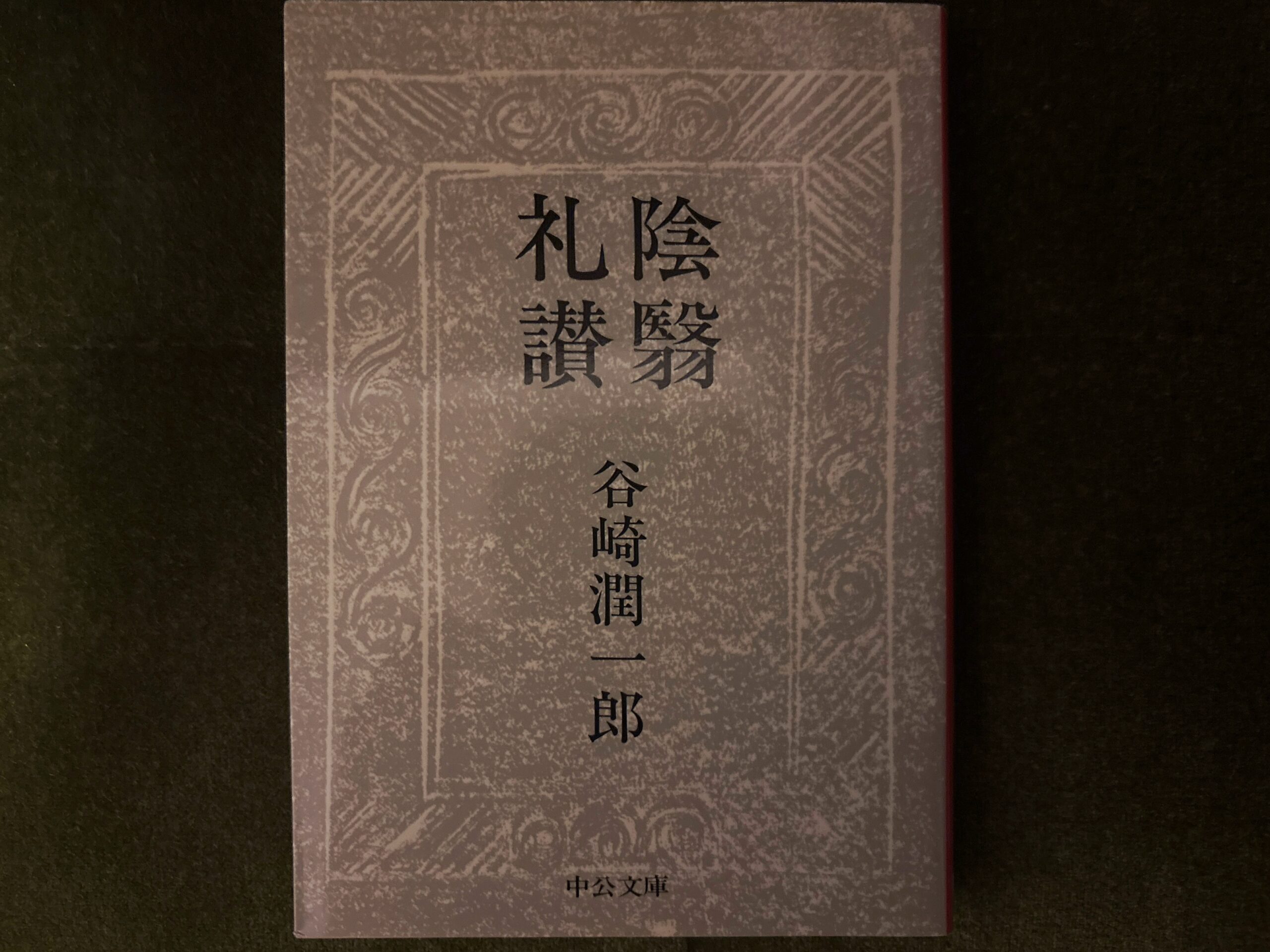1.翳りの中に美しさを見出す谷崎の傑作エッセイ
今日紹介するのは谷崎潤一郎「陰翳礼讃」。
この本は、近代化によって急速に浸透しつつあった西洋文化に対して「陰翳」に潜む美意識と奥深さについてのエッセイだ。
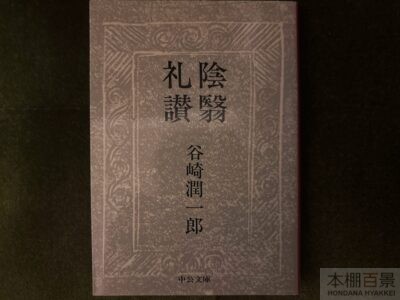
著者の谷崎潤一郎といえば近代日本を代表する文豪のひとりだけれど、この陰翳礼讃には谷崎のエッセンスが詰まっている。
はじめて陰翳礼讃を読んだのは大学生の時だったが、まず感じたことは「暗さや陰をここまで賛美するのか」という驚きだった。
谷崎は日本古来の建築物、漆器の艶、和紙の柔らかい光の反射等に宿る静謐な美を讃える。
そしてその美しさは、直接的な照明ではなく、間接光や反射の中に見出される「陰翳の文化」によるものであると論じるのだ。
近代化によって電気照明が普及し、身の回りからは急速に「陰」が失われている。
西洋文化は明るさこそ正義、といわんばかりに何でもかんでもくまなく照らしだす世を谷崎は強く批判する。
谷崎は現代の感覚では「暗い」「不便」と切り捨てられてしまいそうな空間に人の気配や時間の流れ、そして「美」を見出す。
光がすべてを暴き立てるのではなく、むしろ見えないからこそ、想像力が広がる余白があるというのが谷崎の主張である。

この想像力が広がる余白というのは、考えてみれば思い当たる節がある。
例えば小さい頃、おばあちゃんの家に泊まった日の夜、寝床について天井を見上げるとぼんやりとした闇があって怖かった思い出がそうだ。
特に天井の隅は闇が一層濃くなっていて、おばけか妖怪かこの世のものでないのもがいるのではないかと恐ろしくなったものだ。
2.「まっくろくろすけ」を生み出す想像力
陰に潜む魑魅魍魎といえば、となりのトトロにでてくる「まっくろくろすけ」もその一つだろう。
昔の日本家屋には、どこかこのまっくろくろすけがいるのではないかと思わせるリアリティがあった。
照明によって隅々まで照らされた部屋にはまっくろくろすけは出てこない。いや、出てくる余地がないのだ。

陰翳礼讃の中で特に面白いのは、昔ながらの日本の厠(便所)を絶賛するくだりだろう。
これがまた妙に説得力があって笑ってしまうのだが、よく読むと彼の言っていることは本質的だ。
人が「不快」と感じるものの中にも、静けさや余韻があり、その空間にしか生まれない気分や詩情がある。
それを丸ごと排除してしまうのが、文明というものの残酷さでもある。
最後に谷崎は、この失われつつある陰翳の美学を自分は文学で実践していくと締めくくっているのもいい。
谷崎の小説には陰を抱えている者が多く登場するし、谷崎の小説にはまさに厠のような汚さ、気持ち悪さ、そしてエロティシズムがある。
しかしその分、その陰りに想像力が広がり奥深さが感じられるのだ。
谷崎の文学は好き嫌いが分かれがちといわれるが、「陰翳礼讃」はそんな谷崎文学の格好の補助線にもなる。
「陰翳礼讃」は単なる懐古趣味ではない。
それは消えゆく美に対する鋭い考察であり、光の裏側に確かに存在する陰りと、人間の想像力に対する賛歌なのである。
にほんブログ村
書店ランキング
↑読書・書店のブログランキングに参加しています。よければクリックして応援してもらえると嬉しいです。
本やブックスポット好きな人は、他にも面白い本・読書ブログもいっぱいあるので、是非クリックして覗いてみてくださいね。